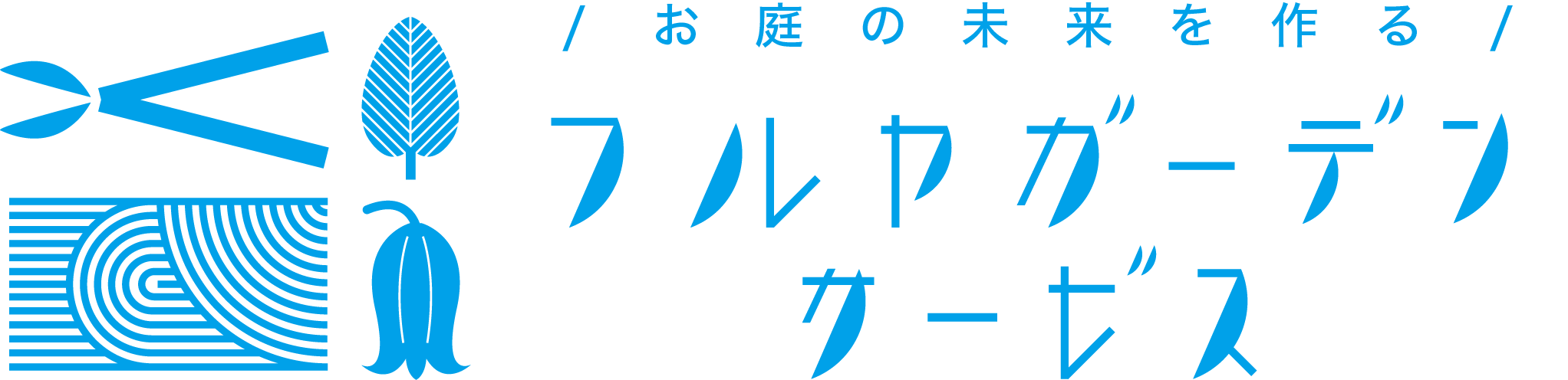今回は狭小地の支柱設置についてご紹介します。
そもそも支柱はなぜ必要なのか・・・
植栽用に入手した木は、鉢植えだったり、根巻(根鉢に合わせて根がカットされ、麻布などで植え土ごとくるまれている状態)されていたりします。
そのような状態から、木が新たな土地に植えられ、しっかりと根を張るまでには時間がかかります。
その間に木がぐらぐらしたりすると、せっかく出てきた若く細く柔らかな根が切れてしまい、根付くことができず、やがて弱ってしまったりします。
多少の風などでは幹をゆすられても影響なく根をしっかりと張ることができるようにするため、支柱を設置する必要があるのです。
また、木が育ってきてから、元の支柱が効かなくなり木が傾くようになってしまい、再度矯正したいような場合にも新たにかけなおす場合があります。
小さな苗木などは添え木などで十分な場合が多いのですが、そこそこ大きな木を植え付ける場合は、八掛け支柱などを設置します。
これは木を3本の竹でささえるもので、比較的しっかりと木を支えることができます。
下記はYが以前植え付けた樹木と八掛け支柱です。
さて、八掛け支柱以外には竹を1本だけ使ったものや2本で支えるものなどがありますが、これらはあまり大きくない木に使われます。
また、列植などの場合は布掛け支柱(2本以上の垂直に立てた柱に水平に竹を渡して取り付け、この竹に木を括り付けるもの。何本もの木を括り付けることができるので列植向き。)をすることもあります。
木の大きさや植え付け方などでこれらの支柱を使い分けるのですが・・・
八掛けしたいが、物理的にどうしても無理、という場合もあります。
前の画像にもあるように、八掛け支柱は割と場所を取ります。
駐車場や道路、ブロックなどの外構構造物に囲まれた狭い植栽地に植えられている木では、無理な場合がほとんどです。
画像は剪定とともにご依頼をいただいたのですが、家と道路の間50cmほどの植栽エリアに植えられたオリーブとユーカリが大きくなりすぎて道路側に垂れてしまい、何とかしてほしい、というものでした。
オリーブにはもともと八掛け支柱がしてありましたが、あまり深く支柱の根入れができておらず、木にぶら下がっているような状況でした。
植えられている根元を見ると、桝やメーター、機能門柱などが所狭しとあり、間を縫って植栽がある様子。
升が複数あるといううことは土の中には管が通っていますし、機能門柱があるということは、インターフォンの配線があることを意味します。
無理をして竹を打ち込むとこれらを壊してしまう可能性がありますので、効き目があって、これらを壊すことのいない安全な支柱をよく考えて行う必要があります。
これらの管が通っていたり、反対側には家の基礎がはいっていたりすることを考えると、そもそも八掛けは無理そうです。
何とか竹を打ち込むことができるのは限られた場所のみなので、今回は布掛け支柱を応用することにしました。
二本の柱で支えていますが、安全な場所を選び、しっかりと効くように比較的深く打ち込んでいますので、効き目は十分です。
正面から
横から